[問] 私たちはFAの機械を設計から製作、受注、納品まで行うメーカーです。この中で、PLC制御に関わる人を電気屋さんと呼んでいるのですが、何か問題がるのか嫌がられます。 どうしたものでしょう
⚡ なぜ「電気屋さん」と呼ばれるのを嫌がるのか
- 専門性の誤解 「電気屋さん」という言葉は一般的に「配線工事をする人」「電気工事士」といったイメージが強く、PLC制御やソフト設計のような高度な技術を軽視しているように聞こえることがあります。
- 職種のアイデンティティ PLC制御担当者は「制御設計者」「システムエンジニア」としての誇りを持っています。そこを「電気屋さん」とまとめてしまうと、自分の専門性が正しく認識されていないと感じる人がいます。
- 社外との混同 社外の協力会社や顧客に「電気屋さん」と言うと、電気工事業者と誤解される可能性があり、業務範囲が正しく伝わらないことがあります。
✅ どうすればよいか
- 呼び方を整理する
- 「制御担当」
- 「PLCエンジニア」
- 「電気制御設計」
- 「制御ソフト担当」 など、業務内容に即した呼び方にすると誤解が減ります。
- 社内文化として定着させる 社内で「電気屋さん」と呼ぶのは親しみからかもしれませんが、本人が嫌がるなら「正式な呼び方」をルール化して、社内文書や会議でも統一すると良いです。
- 尊重の姿勢を示す 「電気屋さん」と呼ぶ代わりに「制御のプロ」といったニュアンスを込めて呼ぶと、専門性を認めていることが伝わりやすいです。
💡 提案
例えば、社内で「機械屋さん」「電気屋さん」と分けたいなら、
- 「機械設計チーム」
- 「制御設計チーム」 といった チーム名ベース にすると自然で、本人も誇りを持ちやすいです。
つまり、「電気屋さん」という呼び方自体が悪いわけではなく、専門性を軽んじているように聞こえることが問題なんです。呼び方を少し工夫するだけで、社内の雰囲気もぐっと良くなると思います。
[問] 電気設計と言っても 電機制御と言っても嫌がられます
なるほど、そこまで言葉に敏感に反応されるのですね。これは単なる呼び方の問題というより、職種のアイデンティティや専門性の認識に関わる部分が大きいと思います。
🔍 なぜ「電気設計」「電機制御」でも嫌がられるのか
- 「電気設計」=配線図や盤設計のイメージ 制御ソフトやPLCプログラムを作る人からすると、自分の仕事が「配線図を書く人」と混同されているように感じる。
- 「電機制御」=古い呼び方や曖昧さ 「電機」という言葉は業界によっては機械電気系を指すこともあり、制御ソフトの専門性が伝わりにくい。
- 本人たちのプライド PLC制御は「ソフト設計」「システム設計」に近い領域で、機械設計と同じく高度な設計業務。そこを「電気屋さん」や「電気設計」とまとめられると、自分の専門が正しく認識されていないと感じる。
✅ 解決の方向性
呼び方を「電気」ベースから少し離すと、受け入れられやすくなります。
- より専門性を反映した呼び方
- 「制御設計」
- 「PLCソフト設計」
- 「制御エンジニア」
- 「オートメーション担当」
- 「システム制御」
- チーム名で整理する
- 「機械設計チーム」 vs 「制御設計チーム」
- 「メカ担当」 vs 「コントロール担当」
- 本人たちに選んでもらう 社内でアンケートや話し合いをして「どう呼ばれるのが一番しっくりくるか」を決めると、納得感が出ます。
💡 提案
「電気」という言葉を避けて、“制御”や“システム”を軸にした呼び方に変えるのが一番スムーズです。 例えば「制御設計チーム」とすれば、機械設計と対等な設計業務として認識されやすく、本人たちも誇りを持ちやすいでしょう。
👉 もし御社で「機械屋さん」と呼ぶ文化を残したいなら、ペアで「制御屋さん」と呼ぶのも一案です。親しみは残しつつ、専門性を軽視していないニュアンスになります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あえて言おう
まぁ、日本での正式呼称の定着はむりゲーだね
”俺様はぜんぶやってるけどな!”へへへw

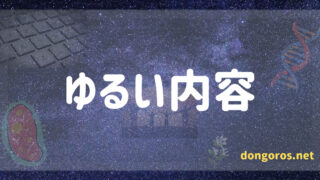
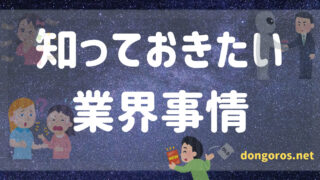
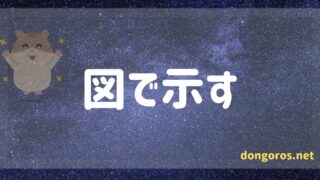
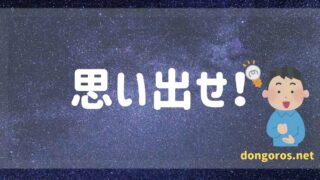



コメント